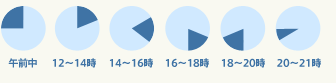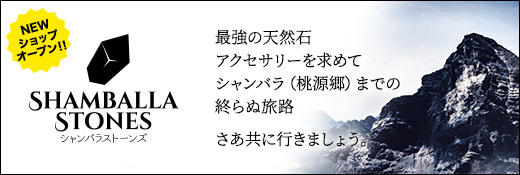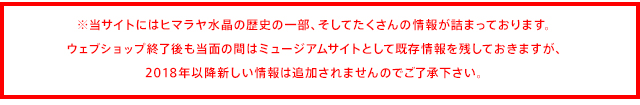
その他ヒマラヤ産天然石解説
ヒマラヤ周辺が実は豊かな鉱物地帯であるということが知られたのは最近です。 近年のヒマラヤ水晶ブームにより、現地でもヒマラヤ水晶・ヒマラヤ産鉱物関連業界が活気付き、様々な影響を与え合いながら市場は急激に拡大しました。 いまや水晶だけでなく、色々な天然石がヒマラヤからやってきています。 しかしながら鉱山のほとんどが自然環境の厳しい高地であり、採掘は困難を極めます。 たとえ埋蔵量が多くても大規模な採掘は不可能と思われ、世界の鉱物地図を塗り替えるほどの産出量にはならないでしょう。
質・クオリティに至っては世界の他の産地のものよりも低いにもかかわらず、ヒマラヤ産というだけで高額である天然石や鉱物も中にはございます。 遥かヒマラヤ山中からやってきたという事実に想いを馳せ、それら希少な天然石をお楽しみ頂ければ幸いです。 また、解説のネパール・ヒマラヤ部分の記述はすべてスパイキーの長年の現地調査や経験に元基づき、オリジナルで執筆したものです。 下記の専門英字文献を除き、他社様、他個人様サイトは一切参考にしておりません。 情報は流動的ですので、今後の新しい情報により記述は随時更新・変更していく予定です。 記述に誤りがある可能性もございますし、あくまで当店独自の解説ということをご理解下さいませ。
その他ヒマラヤ産天然石の解説
【ヒマラヤ産ローズクォーツ】
   | 可愛らしいバラ色ピンクの水晶はローズクォーツと呼ばれます。 日本名は紅水晶。ほのかなピンク色は少量のチタンによるものと考えられておりますが、他の要因でピンク色になるとも指摘され(スモーキーやアメジストと同じ天然照射によるものという説とインクルージョンによるものという説あり)、実はよくわかっていない水晶の一つです。 常に半透明の塊状でペグマタイト中から産出し、面やポイント結晶も見られません。 ローズクォーツは非常に高温で生成(400-700℃)するため、気体(ガス)から生まれると考えられます。 その為、液体から生成される普通の水晶がポイントを持つのに対し、ローズは面やポイントを持ちません。 ちなみにローズクォーツはピンク水晶(Pink Quartz)と呼ばれる水晶とは全く別のものです。 ヒマラヤ産のローズクォーツも例外ではなく、大抵のものは白濁し、曇りやクラックもがあったりします。 当店では、ほとんどの場合、丸玉ビーズやカボション等にカット加工を施します。 しかし、質が良いとされるマダガスカル産などに比べると、ヒマラヤ産のものは白濁も激しく色も薄い傾向にあるように思えます。 ヒマラヤ産ローズの価値は「それがヒマラヤ産である」ということのみと言えるでしょう。 主な産地はチベット国境近くのシンドゥパルショークのペグマタイト鉱床ですが、他の地区でも産出するという話がございます(スパイキーパサルではシンドゥパルチョーク産以外は取り扱っておりませんが) 2008年ごろまでは比較的手に入りやすかったように思えますが、その後急激に無くなり、産地からの到着も途絶えました。 以来2012年末まで一度も入荷の話がございません。 シンドゥパルチョークでの産出は尽きた、もしくは鉱夫が居なくなったのでは、と考えております。 以降も新たに入荷する可能性は低いといえるでしょう。 |
|---|
【アメジスト(マーブルアメジスト)】
   | 紫色の水晶といえばアメジストです。 ギリシャ語の「酒に酔わない=a-methy-stos」という言葉が由縁なのは有名な話ですが、この紫色は結晶構造格子に鉄イオンが入り込み、化学的変化のプロセスを経たものだと考えられます。一様な色のスモーキーとは対照的に、アメジストは色がむらになるケースが一般的です。 ヒマラヤ産のアメジストも例外ではなく、紫の色合いに濃淡があり、白から紫までグラデーションになったり、紫色が筋状になっているものもあります。 アメジスト水晶と差異をつけるために、この種のアメジストをマーブルアメジスト(S造語)と呼んでおります。 マーブルアメジストは綺麗にポイント結晶しているものは稀で、ほとんどの場合崩壊している塊状の結晶で産出します。 その為多くはカット加工に回しますが、丸玉やカボションは神秘的で美しい模様を持つものが仕上がります。 かなり昔から時々カトマンズに届くマーブルアメジストですが、供給も不定期で細かなことまではまだわかりません。 ダディン地区のヒンドゥンという場所が産地のようですが、ラパ村の北西方向にあたるようです。 ヒンドゥンではその他スモーキークォーツの産出も聞かれるのですが、2008年頃を境にマーブルアメジストはほとんど無くなってしまいました。 それ以来カトマンズへの到着も入荷もございません。 もともとマーブルアメジストのほとんどが古いもののストックで、近年掘られたものではなく、随分昔に掘られたものだったのではないかという見解に至っております(只今調査中です) その為、今後の入荷もかなり難しいといえるでしょう。 余談ですが、アメジストは紫外線で激しく退色しますので、長時間太陽光にさらすのは厳禁です。 蛍光灯下もNGですので、保管の際は光を避けて暗い場所に置きましょう。 |
|---|
【ヒマラヤ産ガーネット(ざくろ石)】
   | 燃える情熱のような赤い色が印象的なこの石は日本名を柘榴石といいます。 実はこのガーネットという名前は鉱物名ではなく、14種類の鉱物グループの総称のことです。 ガーネットといえば赤色を想像する方も多いと思いますが、この14種類の中にはオレンジや褐色、緑色のものも存在します。 ユニークな産出形状をすることが多く、菱形12面体というコロコロとした形がみられることも珍しくありません(写真参照) 一般的にガーネットとして最も出回っているのはアルマンディンという鉱物です。 ネパール・ヒマラヤ産においてはこのアルマンディンとスペサルティンという種類しか確認しておりませんので、この2つを主に解説します(ネパール鉱物地質学庁の2004年の調べによると、ヘソナイトの産出も確認されているそうです) カボションや丸玉ビーズとして登場しているものはアルマンディンガーネットです。 深いワインレッドですが、光に翳すと少しピンク色っぽくも紫っぽくも見えます。 この赤い色は鉄やクロムといった成分によるものとされています。 アルマンディンはダディン地区とサンクワサバ地区、そしてタプレジュン地区の結晶片岩中や片麻岩中で産出します。 最も多く産出するのはサンクワサバですが、当店のビーズ玉やカボションに使用しているような質の良いガーネットはダディン地区ガネーシュヒマール山のルニール鉱山(ルビーで有名な鉱山です)周辺でしか採れません。 ※2010年にボテコシという産地のガーネットを確認しましたが、こちらも内部が透明で非常に綺麗なものでした。 只今調査中です。 また、タプレジュン地区のペグマタイト鉱床では水晶に内包された状態でも産出します。 水晶用語解説内包物編:ガーネット入り水晶もご参照ください。 |
|---|
【ヒマラヤ産アクアマリン(緑柱石)】
   | アクアマリンとは、海のように美しい水色から名づけられた宝石名(通称)であり、鉱物名はベリルといいます。 和名は緑柱石。 色が濃いアクアマリンほど好まれる傾向にあり、最高質のアクアブルーをかつて良質を産出したブラジルの鉱山に因んで「サンタマリア」と呼ぶことがあります。 カット加工され、宝石として市場に出回っているものは熱処理(エンハンスメント)によって色を濃くしているものがほとんどです。 天然のものの多くは内部が白濁していたり、緑色が強いのですが、良質のものは綺麗な6方結晶(6柱状)を成し、透明で美しい水色をしています。 ネパール・ヒマラヤにおいてアクアマリンは比較的産出の多い石であり、ほぼ全域にわたってヒマラヤ高地結晶質岩に属する片岩や片麻岩中のペグマタイト鉱床からの産出が確認されています。 しかし上質なものは稀で、最も質の高いものが産出するのはタプレジュン地区のカンチェンジュンガ山です。 特にパティバラ(3794m)以高の高地(イカブ・サンサブ地域やロダンタール地域)では良質で面白いアクアマリンが産出します。 次いでサンクワサバ地区のヒャクレイ地域やマナン地区のナジェ地域でも質の高いアクアマリンが産出します。 これらの地域からくるアクアマリンは天然結晶でも色が濃いうえに透明度も高いもの、6柱形状もしっかりしたものや、水晶に貫入したアクアマリン、白雲母に埋もれたアクアマリンや、ショールトルマリンと共存するアクアマリンなど、世界でも充分に通用するユニークで面白いアクアマリンが採れます。 しかしカンチェンジュンガのアクアマリンは採掘が困難な高地からの産出ということもあり、非常に高額で取引されるのが現状です。 現地ではカンチェンジュンガのアクアの特徴として、結晶内に十字に交差する霧状のもやがあるといわれておりますが(写真参照:十字というよりもXXXのような感じ→当店ではカンチェンクロスと呼んでいます)これが果たして本当にカンチェンジュンガのアクアだけに現れる特徴なのかは、わかりません。 その他の地区や地域でも産出がありますが、その他の地域のアクアマリンはほとんどが白んでいたり、結晶が崩壊しているものです。 また、最近パキスタンからアクアマリンが入ってきており、「ヒマラヤ産」として売られているという情報が入っております(未確認)ので注意が必要です。 |
|---|
【ヒマラヤ産アクアマリンキャッツアイ】
  | アクアマリンの中には光を反射することによって猫目石のように一本線がはいるものがあります。 これをアクアマリンキャッツアイと呼びますが、希少性も高いく、レアな石といえるでしょう。 キャッツアイ効果は不透明な繊維状組織の内包(または鉱物の結晶状態が繊維状組織そのもの) によって、繊維状組織が光の反射をおこすことによって現れます。 内包された繊維状組織がシャトーヤンシー効果を生むので、 透明であれば、キャッツは薄く、キャッツが濃ければ透明度は無い、というのが一般的です。 アクアマリンのあるところにアクアマリンキャッツが出る可能性があるので、ネパール・ヒマラヤにおけるアクアマリンキャッツアイの主たる産地もタプレジュン地区やサンクワサバ地区となります。 大きなものや色が非常に美しいものも稀に出てきますので、ネパールのアクアキャッツを侮ってはいけませんね。 |
|---|
【ヒマラヤ産ゴシュナイト&ヘリオドール(その他のベリル・緑柱石)】
  | アクアマリンと同じベリルでも色によって宝石名が変ります。 黄色や金色のベリルをヘリオド−ル(Heliodor)と呼び、ギリシャ語の太陽への捧げものという意味を持ちます。 この黄色は鉄分による色合いだと考えられています。 ヘリオドールはペグマタイト鉱床にアクアマリンと共に産出します。 ゴシュナイト(ゴシャナイト)は無色透明のベリルに与えられた宝石名です。 通常は他の色が混ざったり不純物が混ざることが多いため、純粋な無色透明のゴシュナイトは希少価値が高いといえます。 ネパール・ヒマラヤ産において確認されているアクアマリン以外のベリル鉱物はヘリオドールとゴシュナイトのみです。 これらの希少なベリル鉱物は、宝石質アクアマリンやトルマリンの産出が見込まれるサンクワサバ地区やタプレジュン地区、ジャジャコット地区のペグマタイトを調査採掘中に、偶発的かつ単発的に産出するケースがほとんどのようです。 現在に至るまで、規模が大きく商業としての価値があるアクアマリン以外のベリル鉱床は見つかっておりません。 よってこれらのヒマラヤ産希少ベリルは非常に珍しいといえます。 左写真はスパイキーパサルの私物ゴシュナイトですが、この大きさのゴシュナイトを手に入れることはほぼ不可能です。 ※ゴシュナイトはアクアマリンの内部にごく稀に生成される透明部分を削りだして作られることもあります。 この場合は、アクアマリン色から透明になってくグラデーションを帯びている事もあり、世にも美しいゴシュナイトが出来上がることがあります。 |
|---|
【ヒマラヤ産カイヤナイト(藍晶石)】
  | 和名藍晶石という名のとおりインディゴブルー(藍色)の鉱物で、片岩や片麻岩といった変成岩中に産出します。 カイヤナイトは、方向によって硬度が異なるという少し変わった鉱物ですが、原石を見たときに平べったい面が高度7の面、デコボコの面が高度5の面です。 繊維状組織で崩壊質、不透明なことが多く、ほとんどの原石は加工に適しませんが、良質なものは透明感があり、カット加工を施すと鮮やかな藍色のグラデーションを示します。 ネパール・ヒマラヤ産において、カイアナイトは産出が多い鉱物の一つといえるでしょう。 ネパール全域においてヒマラヤ高地結晶質岩の変成岩中に産出があるようですが、埋蔵量が豊富なのはジャジャコット地区とサンクワサバ地区の片岩中です。 特にサンクワサバ地区から来るカイアナイトは稀に質の非常に良いものがあり、カボションカットやファセットカットを施すと、驚くほどに美しい宝石へと生まれ変わります。 中にはサファイアのように濃いブルーを見せるものや、天然の縦縞模様が綺麗なグラデーションを作るものなどがあります。 これらヒマラヤの良質カイアナイトは世界に誇れるカイアナイトだと言えるでしょう。 全体的な埋蔵量は多いとはいえ、宝石質カイヤナイトはなかなかの希少品です。 もともとカイアナイトに対して「綺麗な石」という概念を持っている方は少ないと思いますが、ヒマラヤ産のカイアナイトはその概念を見事に覆してくれるはずです。 |
|---|
【ヒマラヤ産ハンベルジャイト(ハンベルグ石)】
 | ハンベルガイト、ハンバーガイト等呼び名は様々ですが、スウェーデン鉱物学者・アクセルハンベルグに因んで名づけられました。 日本名はハンベルグ石。 原石は半透明で白濁しており、伸長方向に条線が入っています。 宝石質とされる透明部分を持つものはごく稀で、非常に脆い性質をもちますので、カットには適しません。 しかしコレクターの間では人気が高く、蒐集品のひとつです。 ネパール・ヒマラヤ産においては、マナン地区とサンクワサバ地区で産出が確認されています。 原石は見かけますが宝石質でファセットしてあるものは稀で、かなりの高額で取引されます。 かつては宝石質の良質もありましたが、産出が減っている為、現在市場に流れているものはストックからの放出が多いようです。 |
|---|
【ヒマラヤ産ショールトルマリン・黒いトルマリン(電気石)】
  | トルマリンの中でも不透明で黒いトルマリンをショールと呼びます(※これは鉱物としての名前ではなく、宝石名としての通称です) 熱すると電気を帯びる為、日本名を電気石といいます。 黒色の原因は鉄分であり、縦方向に条線をもつ柱状で産出する場合が多い。 透明度が無く、黒色ということから、カット加工を施しても宝石としての価値はあまりありません。 タプレジュン地区のカンチェンジュンガ山・ペグマタイト鉱床が広がるイカブ地区やロダンタール地区がショールの良質を産するとして有名です。 この地区のショールは照りが強く、形状もしっかりとしているものが多く、水晶と共生しているものや、長石母岩がついているもの、ガーネットやアクアマリンを伴ったものなど、非常に面白いものが見つかっています。 しかしかつては多く採れたショールも減少傾向にあり、今後は少なくなると思われる石のひとつです。 |
|---|
【ヒマラヤ産ドラバイト・ブラウントルマリン(苔土電気石)】
  | トルマリンの中でもブラウンのものをドラバイトと呼びます。 マグネシウムの含有が褐色を作り出すとされており、角度によって深いブラウンからオレンジ、イエローのようにも見えます。 ネパール・ヒマラヤ産においては、ジャジャコット地区に産出し、産出量は多いといえます。 ティカチョールといわれる地域のようですが、詳しいことは現在調査中。 ジャジャコット地区のドラバイトは2-3cmの結晶がコロコロと産出するような産状で、表面には艶が無く、ひび割れていることが多いため、原石としての魅力には若干乏しいといえます。 スパイキーでもほとんどを丸玉ビーズやカボションカット加工しています。 カットを施すと、イエローからブラウンまでの多色性を示し、魅力的な宝石に様変わりします。 稀にアンバー(琥珀)のような神秘的山吹色のものがありますが、これは非常に魅力的と言えます。 ドラバイトの産出はその他タプレジュン地区とイラム地区にもあるようですが、詳細は不明。 |
|---|
【ヒマラヤ産カナリア・イエロートルマリン(電気石)】
  | 黄色い鳥、カナリアに因んでイエロートルマリンをカナリアと呼ぶことがあります。 これも鉱物名ではなく、宝石としての通称です。 イエロートルマリンはほとんどがマナン地区のナジェ地域からやってきます。 良質のイエロートルマリンはまさにカナリアのような鮮やかな色を発し、カボションカットやファセットカットとして市場に出回っています。 原石は崩壊質でしっかりした結晶を持つことが少ない為、もっぱらカット加工されます。 また、マナンのトルマリンは多色性を示しているものもあり、イエローとブラウンの2色トルマリンや、ピンクとイエローが混ざったトルマリンなど、美しく魅力的なトルマリンが存在します。 同じように多色性を示すイエロートルマリンはサンクワサバ地区でも産出していました(現在閉山中) かつては多くあったマナンのトルマリンですが、最近では全くもって新しいものを見かけません。 古くからの業者が古くからのストックを持っているのみというのが現状と言えるでしょう。 こちらの鉱山もすでに枯渇または閉山していると考えられます。 |
|---|
【ヒマラヤ産マルチカラートルマリンや希少トルマリン(電気石)】
   | ネパール・ヒマラヤにはその他珍しいトルマリンも産出します。 ヒマラヤトルマリンの聖地として名高いヒャクレイ地域(鉱山2153m)では、1956年から約8年間採掘がおこなわれ、延べ1300キロ(うち宝石質は10%程度と言われる)の産出があったと記録されています。 このヒャクレイ地域のペグマタイト鉱床は広大であり、今でも宝石質トルマリンの埋蔵が推測されますが、現在は度重なる地崩れにより鉱山は完全に閉山中となっております。 以下の解説に登場する希少ヒマラヤ産トルマリンはすべてサンクワサバ地区のヒャクレイ地区とファクア地区のものですが、現存するヒャクレイ・ファクアのトルマリンは新しく産出したものではなく、すべて50年代に産出されたもののストックとなります。無色透明のトルマリンをアクロアイトと呼びますが、多色・有色性を示しやすいトルマリンにおいて、透明なものは非常に稀産で高価です。 次いで神秘的な藍色のインディゴライトの産出も記録があります。 美しい500カラットのヒャクレイ地区産トルマリンがドイツ人コレクターに渡ったとか。 また、ウォーターメロントルマリンといわれる赤と緑が綺麗に分かれているトルマリンや、一つの柱状結晶で3色4色といった多色を持つ、パーティーカラー(マルチカラー)トルマリンなども存在します。 ヒャクレイ・ファクアのトルマリンは強い多色性に特徴があるといわれており、見る角度によって濃く見えたり薄く見えたり、違う色に見えてりする特性があることが分かっています。 その他、カボションカットを施すとキャッツアイ効果を示すトルマリンキャッツアイも確認されています。 鉱山の閉鎖により、只今市場に出回るのはかつてのストックものとなっておりますが、ヒャクレイ周辺では今も細々と村人が掘っているそうです。 小さな産出は稀にあるようですが、未だ大きな鉱床にはぶつかっていないようです。 今後地崩れの土砂が取り除かれ、ヒャクレイの採掘が再開することになれば、また素晴らしいトルマリンたちに出会えるのかもしれません。 |
|---|
【ヒマラヤ産ルビー(コランダム)】
   | 宝石としてはダイヤモンドに次いで価値のある石とされるルビー。 ルビーという名前は宝石における呼称であり、宝石質の赤い色のコランダムのことを指します。 クロムと鉄の含有により赤からピンクまで様々な色調を持ちますが、赤いものほど価値があるとされ、ミャンマー産の最高質のものは「ビショップブラッド(鳩の血)」という異名を持ちます。 世界中の火成岩、変成岩中に産しますが、宝石となるような良質のものは決して多くありません。 ネパール・ヒマラヤ産においては採掘の歴史が非常に浅く、ガネーシュヒマールでその存在が確認されたのは、1980年初頭のことです。 ある程度の埋蔵量が期待されていましたが、採掘場が非常に高地であるということや、自然環境の厳しさから、大規模な採掘は大変困難となっております。 特にチュマール鉱(約3800m)とルニール鉱(約4200m)のヒマラヤ高地変成岩地帯が採掘場となっておりますが、チュマール鉱のほうが良質のものが産し、ルニール鉱のほうが産出量は多いというのがわかっております(84年クリストファースミス博士調査) しかしながら良質を産するチュマール鉱はもともとの埋蔵量も少なく、現在では完全枯渇状態となっております。 従って宝石質のルビーサファイアもヒャクレイ地域のトルマリン同様に市場にあるものはすべて80年代に採掘されたストックものであり、最高質のものはすべてヨーロッパの蒐集家などに流出してしまっております(ちなみに当店でも最高質のものをひとつ保持しております) ルニール周辺では今も若干ながら採掘がおこなわれておりますが、透明度のある宝石質は残念ながら産出しておりません。 この産地の特徴として、ひとつの石でカラーゾーニングが激しいということが上げられます。 ルビー色のボディに紫を帯びた青色が混ざり合うことがあり、強い2色性を示します。 この為、ルビーサファイアと呼ばれることがあります(但し、世界のその他の産地でも2色性を示すルビーやファンシーサファイアは確認されていますので、一概にネパールのルビーのみを示す特徴ではありません) 余談ではありますが、チュマール周辺やルニール周辺では80年代から90年代に激しく乱掘され、遠くから見ても場所が確認できるほど岩肌が露出してしまっております。 |
|---|
   | 【ヒマラヤ産サファイア(コランダム)】ルビー同様にサファイアとは宝石質コランダムを指す宝石名であり、赤以外の色のコランダムをサファイアと呼びます。 やはり深い青色のものが最も価値が高いのですが、その他にも無色サファイアやイエローサファイアなど、含有物の具合によって様々な色を示します。 一大産地はミャンマーですが、インドのカシミール地方にのみ産するサファイアはカシミールブルーと呼ばれ、コレクターアイテムになっています。ネパール・ヒマラヤにおいてはタプレジュン地区にサファイアの産出があります。 カンチェンジュンガ近くのクプタールというところは通称「サファイアヒル(サファイアの丘)」と呼ばれ、かつては多くを産出しましたが、今はほとんど底を尽きた状態です。 残念ながらこのサファイアヒルのものは宝石質や大きな結晶が稀で、ほとんどが不透明で紫を帯びた薄ブルーに強い縞模様を示したものです。 筆者もファセットカットされた宝石としてのサファイアは見たことがございませんが、カボションであれば色の良いものも存在します。 良質のものは今後より手に入りにくくなると思われ、希少といえるでしょう。 通常見かけるタプレジュン地区クプタール産サファイアのほとんどは、紫を帯びた水色で不透明なものです。 しかしながらこの紫みを帯びた水色が非常に優美な色合いであり、カットしてビーズ加工するととても綺麗なものに仕上がります。 この色こそが「ヒマラヤ産」サファイアらしさであるではないでしょうか。 |
|---|
※天然石・鉱物の一般的情報やデータは「宝石の写真図鑑」日本ヴォーグ社、「たのしい鉱物と宝石の博学辞典」日本実業出版社、一部専門知識を要するヒマラヤ系鉱物の解説はGem&Gemology VolumeXXXIII SPRING1997 C.P.Smith、Mineral Resources of Nepal, Dept of Mines and Geology August 2004 ediciton, The mineral Record, vol16 September-October, 1985 A.M Bassettを参照・一部和訳させて頂きました。
※当店の記述を流用・転用する場合は個人様、業者様に関わらず必ずご一報下さいますよう宜しくお願い致します。 当店の情報を流用するとそれが当店のものであるということがわかるようになっております。





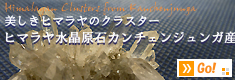
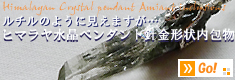





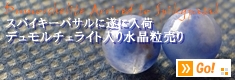
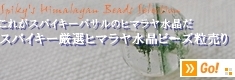

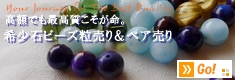

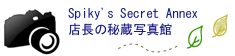


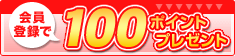




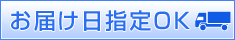
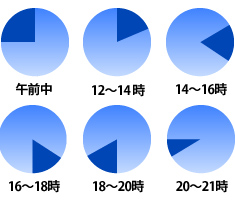

 ターコイズは人類との歴史が最も古い石のひとつで、世界四大文明であるエジプト文明、メソポタミア文明、中南米のアステカや中国の殷王朝など、世界各国の古代遺跡でもターコイズをあしらった装飾品が発見されています。 従ってターコイズ採掘の歴史も古く、イランやシナイ半島の鉱山は2000年以上の長きに渡り採掘が続いている場所もあります。
ターコイズは人類との歴史が最も古い石のひとつで、世界四大文明であるエジプト文明、メソポタミア文明、中南米のアステカや中国の殷王朝など、世界各国の古代遺跡でもターコイズをあしらった装飾品が発見されています。 従ってターコイズ採掘の歴史も古く、イランやシナイ半島の鉱山は2000年以上の長きに渡り採掘が続いている場所もあります。 このターコイズですが、単結晶をなさず(きまった形を持たない隠微晶質といいます)、多くの場合は亀裂や岩石の割れ目などを埋める団塊状で産出します。 化学式は非常に複雑で、水酸化銅アルミニウム燐酸塩CuAl6(PO4)4(OH)8・4H2Oと表されます。 この銅こそが、美しい青色の要因です。 純粋なターコイズほど青色であり、チベットトルコ石のような緑のターコイズは不純物としての鉄の含有によるものです。 不純物が無いものはもちろん良質とされますが、筋状や帯状に広がる黄鉄鉱や褐鉄鉱によって表面に多色性が見られたり、美しい模様が見られるものも好まれます。 褐鉄鉱により蜘蛛の巣のように見える模様は、蜘蛛の巣模様(スパイダーウェブ)と呼ばれ、放射線状に広がる蜘蛛の巣模様は蒐集家に好まれます。 トルコ石は脆い晶質を持つ上に退色を起こす事もありますので、決して強い石とはいえません。 汗や化粧品、強い直射日光には気を付けなければなりませんので直射日光のあたる場所での保管や、汗をかくことが見込まれる際の着用はお控えください。 定期的に柔らかい布などで表面を拭いてあげることが必要です。 また、トルコ石は模倣品の歴史も非常に古く、様々なターコイズ模倣品やエンハンスメント品が出回っております。 油やワックスによる表面のコーティングは可愛いものですが、市場に出回るターコイズの中には練り物(合成品)や、他の石に着色したものが多く存在します。
このターコイズですが、単結晶をなさず(きまった形を持たない隠微晶質といいます)、多くの場合は亀裂や岩石の割れ目などを埋める団塊状で産出します。 化学式は非常に複雑で、水酸化銅アルミニウム燐酸塩CuAl6(PO4)4(OH)8・4H2Oと表されます。 この銅こそが、美しい青色の要因です。 純粋なターコイズほど青色であり、チベットトルコ石のような緑のターコイズは不純物としての鉄の含有によるものです。 不純物が無いものはもちろん良質とされますが、筋状や帯状に広がる黄鉄鉱や褐鉄鉱によって表面に多色性が見られたり、美しい模様が見られるものも好まれます。 褐鉄鉱により蜘蛛の巣のように見える模様は、蜘蛛の巣模様(スパイダーウェブ)と呼ばれ、放射線状に広がる蜘蛛の巣模様は蒐集家に好まれます。 トルコ石は脆い晶質を持つ上に退色を起こす事もありますので、決して強い石とはいえません。 汗や化粧品、強い直射日光には気を付けなければなりませんので直射日光のあたる場所での保管や、汗をかくことが見込まれる際の着用はお控えください。 定期的に柔らかい布などで表面を拭いてあげることが必要です。 また、トルコ石は模倣品の歴史も非常に古く、様々なターコイズ模倣品やエンハンスメント品が出回っております。 油やワックスによる表面のコーティングは可愛いものですが、市場に出回るターコイズの中には練り物(合成品)や、他の石に着色したものが多く存在します。 当店の扱うターコイズは、すべてチベットで愛用されていたアンティークターコイズです(※カボションペンダントに使用しているカボションターコイズはチベット産ですがアンティークではありません) チベットにおいては青色のみならず、深い緑色も好まれる傾向にあります。 チベットでは現ダライラマが輪廻転生でその名を湖面に記したという聖なる湖、ヤムドゥク湖(写真がヤムドゥク湖:筆者撮影)の色をしているとされています。 当店ではそれにちなんで深い緑色のトルコ石を「ヤムドゥクブルー(S造語)」と呼んでいますが、これは当店オリジナルの呼称です。 現地ではトルコ石は戦士を守る護符として、そして財産価値として重宝されてきました。 トルコ石は持ち主に危険が迫ると黒い部分が増えたり、赤茶けた色になって知らせてくれると言われています。 色艶も独特で、古いもの特有のパティーナ(使いこまれたことによって現れる独特の鈍い照り)も見られます。 とにかくひとつひとつが形状も違い、色も違い、表情や模様も違います。 天然らしい表情の豊かさと純朴さ、そして愛情を注がれた事による鈍い照りや独特の摩耗形状などはアンティークのチべタンターコイズならではといえるでしょう。
当店の扱うターコイズは、すべてチベットで愛用されていたアンティークターコイズです(※カボションペンダントに使用しているカボションターコイズはチベット産ですがアンティークではありません) チベットにおいては青色のみならず、深い緑色も好まれる傾向にあります。 チベットでは現ダライラマが輪廻転生でその名を湖面に記したという聖なる湖、ヤムドゥク湖(写真がヤムドゥク湖:筆者撮影)の色をしているとされています。 当店ではそれにちなんで深い緑色のトルコ石を「ヤムドゥクブルー(S造語)」と呼んでいますが、これは当店オリジナルの呼称です。 現地ではトルコ石は戦士を守る護符として、そして財産価値として重宝されてきました。 トルコ石は持ち主に危険が迫ると黒い部分が増えたり、赤茶けた色になって知らせてくれると言われています。 色艶も独特で、古いもの特有のパティーナ(使いこまれたことによって現れる独特の鈍い照り)も見られます。 とにかくひとつひとつが形状も違い、色も違い、表情や模様も違います。 天然らしい表情の豊かさと純朴さ、そして愛情を注がれた事による鈍い照りや独特の摩耗形状などはアンティークのチべタンターコイズならではといえるでしょう。 当店で扱うトルコ石はすべて天然アンティーク良質ものです。 多くのものは200−300年前からネックレス等の装飾品として愛用されてきたものです(すべてにビーズ穴が通っているのはその為です) ★4以上のグレードになると、現地での入手も容易ではなく、万が一見つけたとしても、たちまち足元を見られ高額を請求されるでしょう。 トルコ石は通常グラム単位で取引され、色の良さは当然ですが、古いものほど価値があります。 また、大きなものは希少であり、大きなものほどグラム単価が上がる傾向にあります。 最近では巧妙に作られた中国からの偽アンティークも出回っております。 この偽アンティークは驚くほど巧妙で、パティーナの感じまで忠実に再現されているので、本物の中にひとつ程度が混ざってしまっても見分けるのは困難でしょう。 アンティークターコイズの値段は年々着実に上昇している上、絶対数は常に減少していきます。 最近では★5グレードのターコイズもなかなか手に入れられなくなってしまいました。 無くなってしまえば、もう作ることができないのがアンティーク…もし良いものに出会ったら決断してしまうことをお勧めします。
当店で扱うトルコ石はすべて天然アンティーク良質ものです。 多くのものは200−300年前からネックレス等の装飾品として愛用されてきたものです(すべてにビーズ穴が通っているのはその為です) ★4以上のグレードになると、現地での入手も容易ではなく、万が一見つけたとしても、たちまち足元を見られ高額を請求されるでしょう。 トルコ石は通常グラム単位で取引され、色の良さは当然ですが、古いものほど価値があります。 また、大きなものは希少であり、大きなものほどグラム単価が上がる傾向にあります。 最近では巧妙に作られた中国からの偽アンティークも出回っております。 この偽アンティークは驚くほど巧妙で、パティーナの感じまで忠実に再現されているので、本物の中にひとつ程度が混ざってしまっても見分けるのは困難でしょう。 アンティークターコイズの値段は年々着実に上昇している上、絶対数は常に減少していきます。 最近では★5グレードのターコイズもなかなか手に入れられなくなってしまいました。 無くなってしまえば、もう作ることができないのがアンティーク…もし良いものに出会ったら決断してしまうことをお勧めします。 サンゴってあの珊瑚礁のサンゴ?宝石になるの?と思われる方も多いと思いますが、珊瑚は数千年もの昔から宝飾品として人々に愛されてきました。 珊瑚の装飾品は古代エジプトの遺跡からも発見されており、紀元前のヨーロッパ集落遺跡などからも珊瑚の出土品があったそうです。 日本人との歴史も長く、今でも和装には欠かせない装飾品となっております。 珊瑚は成長するにしたがって枝状に生育していくのですが、その成長に起因して縞や木目模様が表面に形成されます。 その為天然の珊瑚は木目のような模様が見られるのが特徴です。 黒やピンク、白の珊瑚などもありますが、最も価値が高いとされるのは赤い珊瑚です。 同じ赤にも色々な赤があり、原色の赤からオレンジ色を帯びた赤、薄ピンク色や薄紅色など豊かな色調を持ちますが、やはり一番良質とされるのは、原色の燃えるような赤色です。
サンゴってあの珊瑚礁のサンゴ?宝石になるの?と思われる方も多いと思いますが、珊瑚は数千年もの昔から宝飾品として人々に愛されてきました。 珊瑚の装飾品は古代エジプトの遺跡からも発見されており、紀元前のヨーロッパ集落遺跡などからも珊瑚の出土品があったそうです。 日本人との歴史も長く、今でも和装には欠かせない装飾品となっております。 珊瑚は成長するにしたがって枝状に生育していくのですが、その成長に起因して縞や木目模様が表面に形成されます。 その為天然の珊瑚は木目のような模様が見られるのが特徴です。 黒やピンク、白の珊瑚などもありますが、最も価値が高いとされるのは赤い珊瑚です。 同じ赤にも色々な赤があり、原色の赤からオレンジ色を帯びた赤、薄ピンク色や薄紅色など豊かな色調を持ちますが、やはり一番良質とされるのは、原色の燃えるような赤色です。 珊瑚は酸性成分に弱いので、汗を吸収すると退色を起こします。 退色を起こした珊瑚は表面に白い粉が浮き上がったり、色が薄くなります。 しかしまめなお手入れを怠らなければ、退色する事もありません。 スポーツや炊事の際は外していただき、もし汗がついてしまったと感じたら、柔らかい布などで表面を吹いてあげるだけで大丈夫です。 特に長期使用しないときは、綺麗に拭いてから湿気の少ないところに保存してください。 市場に出回る合成サンゴは陶器やプラスチック、着色した骨やゴムなどもございますので注意が必要です。
珊瑚は酸性成分に弱いので、汗を吸収すると退色を起こします。 退色を起こした珊瑚は表面に白い粉が浮き上がったり、色が薄くなります。 しかしまめなお手入れを怠らなければ、退色する事もありません。 スポーツや炊事の際は外していただき、もし汗がついてしまったと感じたら、柔らかい布などで表面を吹いてあげるだけで大丈夫です。 特に長期使用しないときは、綺麗に拭いてから湿気の少ないところに保存してください。 市場に出回る合成サンゴは陶器やプラスチック、着色した骨やゴムなどもございますので注意が必要です。 かつて海の底だったヒマラヤ山中ではその名残として化石化した珊瑚が取れる、そんな伝説も相まって、チベットからの珊瑚は通称「山珊瑚(英語でもTibetan Mountain Coral)」と呼ばれます。 「化石の珊瑚」説は何故か非常に根強く、現地の業者や日本の業者の中にもこれを堂々と謳い文句にしているところもあります。 実際のところ、チベットの山珊瑚は交易品として最も古くは数千年も前に地中海地方からやってきた赤珊瑚なのです。 ローマ帝国時代から数百年に及んで珊瑚の産地である地中海地方からインドに大量に持ち込まれたものがチベットに辿り着いたものです。 特に多くはクシャン朝時代(前1世紀頃)にローマ帝国から当時クシャン朝の領土であったインド北部に交易品としてやってきました。 当時インドの豪族たちは、珊瑚を珍しいものとして挙って買い求めました。 インドとの交易や文化交流が盛んなチベットにも珊瑚が流れ、チベットでも希少品として重宝されるようになったのです。 チベット密教の勃興後、珊瑚は宗教上も重要な位置づけをされるようになり、珊瑚の需要は益々拡大しました。 紀元後100年から700年の間にはシルクロードがヒマラヤ圏にまで拡大し、珊瑚は直接チベットでも交易されるようになりました。 チベットでも赤い珊瑚は非常に人気で、かつては金と同等に取引がされるほどだったそうです。 チベット密教のラマ僧にとっては珊瑚のマラ(お数珠)を持つことはステータスでもありますし、チベット人にとって大きな珊瑚等はその家の権威を示すものでした。 また、珊瑚にも護符の効果があるとされ、魔や悪いもの(病気や怪我も含む)を遠ざけると信じられておりました。
かつて海の底だったヒマラヤ山中ではその名残として化石化した珊瑚が取れる、そんな伝説も相まって、チベットからの珊瑚は通称「山珊瑚(英語でもTibetan Mountain Coral)」と呼ばれます。 「化石の珊瑚」説は何故か非常に根強く、現地の業者や日本の業者の中にもこれを堂々と謳い文句にしているところもあります。 実際のところ、チベットの山珊瑚は交易品として最も古くは数千年も前に地中海地方からやってきた赤珊瑚なのです。 ローマ帝国時代から数百年に及んで珊瑚の産地である地中海地方からインドに大量に持ち込まれたものがチベットに辿り着いたものです。 特に多くはクシャン朝時代(前1世紀頃)にローマ帝国から当時クシャン朝の領土であったインド北部に交易品としてやってきました。 当時インドの豪族たちは、珊瑚を珍しいものとして挙って買い求めました。 インドとの交易や文化交流が盛んなチベットにも珊瑚が流れ、チベットでも希少品として重宝されるようになったのです。 チベット密教の勃興後、珊瑚は宗教上も重要な位置づけをされるようになり、珊瑚の需要は益々拡大しました。 紀元後100年から700年の間にはシルクロードがヒマラヤ圏にまで拡大し、珊瑚は直接チベットでも交易されるようになりました。 チベットでも赤い珊瑚は非常に人気で、かつては金と同等に取引がされるほどだったそうです。 チベット密教のラマ僧にとっては珊瑚のマラ(お数珠)を持つことはステータスでもありますし、チベット人にとって大きな珊瑚等はその家の権威を示すものでした。 また、珊瑚にも護符の効果があるとされ、魔や悪いもの(病気や怪我も含む)を遠ざけると信じられておりました。 その後の話になりますが、1959年のチベット動乱により、多くのチベット人が国を追われて難民となりました。 チベット人が向かった先、それはネパールのカトマンズだったのです。 その後カトマンズは亡命チベット人の聖地となり、それと共にチベットのビーズ類(トルコ石や珊瑚、琥珀や天珠等)がカトマンズに流出されるようになったのです。 その為カトマンズは「最良チベット系ビーズの宝庫」となったのですが、現在では価値あるもののほとんどが海外蒐集家へ流出しており、宝庫はすっかり廃れてしまいました。 今でもチベット人は珊瑚やトルコ石を財産価値と考えて身に着けていますし、ネパールに住むチベット系山岳民族の間でも未だに人気の高いものです。 現在では多くの赤い珊瑚は台湾や香港からやってきていますが、これらはアンティークではありません。 アンティークコーラルは非常に価値があり、古さと色合い(赤いほど良い)と大きさと形が価値の基準となっています。 特に大きいものは非常に手に入りにくく、一粒辺りが大きなものは数十万円単位で取引されるほどです。 年々価格が上昇しているのは、アンティークターコイズと同様であり、絶対数は減る一方です。
その後の話になりますが、1959年のチベット動乱により、多くのチベット人が国を追われて難民となりました。 チベット人が向かった先、それはネパールのカトマンズだったのです。 その後カトマンズは亡命チベット人の聖地となり、それと共にチベットのビーズ類(トルコ石や珊瑚、琥珀や天珠等)がカトマンズに流出されるようになったのです。 その為カトマンズは「最良チベット系ビーズの宝庫」となったのですが、現在では価値あるもののほとんどが海外蒐集家へ流出しており、宝庫はすっかり廃れてしまいました。 今でもチベット人は珊瑚やトルコ石を財産価値と考えて身に着けていますし、ネパールに住むチベット系山岳民族の間でも未だに人気の高いものです。 現在では多くの赤い珊瑚は台湾や香港からやってきていますが、これらはアンティークではありません。 アンティークコーラルは非常に価値があり、古さと色合い(赤いほど良い)と大きさと形が価値の基準となっています。 特に大きいものは非常に手に入りにくく、一粒辺りが大きなものは数十万円単位で取引されるほどです。 年々価格が上昇しているのは、アンティークターコイズと同様であり、絶対数は減る一方です。 チベットではトルコ石や珊瑚と並んで人気の琥珀。 トルコ石は空と水、風を表し、珊瑚の赤色は火、そして琥珀は大地の象徴とされています。 チベット仏教では世界を構成する要素を地・水・火・風・空の5つとしておりますので、これら3種の神器とも言うべき3つの石は自身と世界の真理を繋ぐものとして重宝されてきました。 また災いから身を守る御守として、または富や地位を顕示する象徴物として今でもチベット人やヒマラヤ山岳民族には欠かせないものとなっております。 さて、その琥珀ですが世界的にも人気があり、宝石としての認知も高い石です。 いえ、厳密には石ではなく、木の樹脂が3000万年以上も掛けて(諸説あり)化石化したものです。 その為、琥珀の中には昆虫や植物が取り込まれる事があります。 これらは何千何万年前に、琥珀の樹脂に粘着性があった頃に取り込まれたものになりますので、研究者にとってはまさに「タイムカプセル」のように重宝されるものです。 もちろん重宝するのは学者や研究者だけでなく、宝石コレクターも虫入り琥珀として蒐集品の対象としております。 しかし面白い事に多くの琥珀は木々の生い茂る山中で見つかるのではなく、海近くの河口周辺や河口近くの地層から発見されます。 ※山の中で見つかる琥珀はピットアンバー(山琥珀と呼ばれます)樹脂を残した木はやがて倒れ、地中に埋もれます。 地質的年月を経て、その地層は造山活動等で崩壊して海に達します。 そして琥珀はそこから洗い出されて漂流し、辿りついた場所で見つかることもあれば、海岸や地層で堆積するのです。 またあるものはそのまま海底に堆積し、やがては地殻活動で隆起した地層から見つかるのです。 まさに学生時代に習った地球の地殻活動が琥珀にも反映されているわけです。 チベットの琥珀の話に戻りますが、この琥珀もTibetan Mountain Amber(チベット山琥珀)などと呼ばれ、「チベット産」であるかのような表記があることがあります。 山珊瑚の誤った解説然り、これらの琥珀はチベットの山中で採掘されたものではなく、ほとんどがバルト海沿岸地域やミャンマーからやってきた交易品なのです。 今でもバルト海沿岸は琥珀の一大産地として世界的に有名ですが、ここの琥珀は上記の解説のようなシーアンバー(Sea Amber)です。 残念ながら山で採掘されるピットアンバーでもございません。
チベットではトルコ石や珊瑚と並んで人気の琥珀。 トルコ石は空と水、風を表し、珊瑚の赤色は火、そして琥珀は大地の象徴とされています。 チベット仏教では世界を構成する要素を地・水・火・風・空の5つとしておりますので、これら3種の神器とも言うべき3つの石は自身と世界の真理を繋ぐものとして重宝されてきました。 また災いから身を守る御守として、または富や地位を顕示する象徴物として今でもチベット人やヒマラヤ山岳民族には欠かせないものとなっております。 さて、その琥珀ですが世界的にも人気があり、宝石としての認知も高い石です。 いえ、厳密には石ではなく、木の樹脂が3000万年以上も掛けて(諸説あり)化石化したものです。 その為、琥珀の中には昆虫や植物が取り込まれる事があります。 これらは何千何万年前に、琥珀の樹脂に粘着性があった頃に取り込まれたものになりますので、研究者にとってはまさに「タイムカプセル」のように重宝されるものです。 もちろん重宝するのは学者や研究者だけでなく、宝石コレクターも虫入り琥珀として蒐集品の対象としております。 しかし面白い事に多くの琥珀は木々の生い茂る山中で見つかるのではなく、海近くの河口周辺や河口近くの地層から発見されます。 ※山の中で見つかる琥珀はピットアンバー(山琥珀と呼ばれます)樹脂を残した木はやがて倒れ、地中に埋もれます。 地質的年月を経て、その地層は造山活動等で崩壊して海に達します。 そして琥珀はそこから洗い出されて漂流し、辿りついた場所で見つかることもあれば、海岸や地層で堆積するのです。 またあるものはそのまま海底に堆積し、やがては地殻活動で隆起した地層から見つかるのです。 まさに学生時代に習った地球の地殻活動が琥珀にも反映されているわけです。 チベットの琥珀の話に戻りますが、この琥珀もTibetan Mountain Amber(チベット山琥珀)などと呼ばれ、「チベット産」であるかのような表記があることがあります。 山珊瑚の誤った解説然り、これらの琥珀はチベットの山中で採掘されたものではなく、ほとんどがバルト海沿岸地域やミャンマーからやってきた交易品なのです。 今でもバルト海沿岸は琥珀の一大産地として世界的に有名ですが、ここの琥珀は上記の解説のようなシーアンバー(Sea Amber)です。 残念ながら山で採掘されるピットアンバーでもございません。  前記の通り、琥珀もターコイズや珊瑚同様にチベットでは多大な人気を誇ります。 早くは紀元前2世紀のローマ時代にはシルクロード交易を通じて琥珀がチベットに入ってきたという記録があるようですが、最も交易が栄えたのはシルクロードがヒマラヤ地域にまで達した4世紀頃だと言われます。 一般的にアクセサリーとして琥珀が普及するのはそれ以降の事となります。 8世紀にチベットが仏教化されてから、仏教的要素を取り込むようにしてトルコ石や珊瑚と共に琥珀も浸透していったのでしょう。 当店の扱う琥珀は、「チベットで愛用されていた古い琥珀」になります。 最も古くは1000年を越す琥珀もあるかもしれませんが、厳密な年代を特定することは困難を極めます。 多くのものが500年から200年程度と推測できますが、正確にはわかりませんのでご了承下さい。 チベットやヒマラヤ山岳民族での人気を尻目に日本ではトルコ石や珊瑚に比べて今一つ認知が足りません。 現地においては3種の神器中最も手に入れ難いと言っても過言ではないでしょう。 グラム辺りの単価も非常に高額となります。 只今市場に出回っているものの8割方はチベットで使われていたアンティークではなく、新しいものとなります。新しいものを古加工してそれらしくしているものもありますが、コーパルや加工品が流通しているのも事実です。 見分けるポイントとしては、ターコイズや珊瑚同様に古いもの特有の鈍い照りや摩耗痕になりますが、最も大切なのはやはり「信用」による取引です。
前記の通り、琥珀もターコイズや珊瑚同様にチベットでは多大な人気を誇ります。 早くは紀元前2世紀のローマ時代にはシルクロード交易を通じて琥珀がチベットに入ってきたという記録があるようですが、最も交易が栄えたのはシルクロードがヒマラヤ地域にまで達した4世紀頃だと言われます。 一般的にアクセサリーとして琥珀が普及するのはそれ以降の事となります。 8世紀にチベットが仏教化されてから、仏教的要素を取り込むようにしてトルコ石や珊瑚と共に琥珀も浸透していったのでしょう。 当店の扱う琥珀は、「チベットで愛用されていた古い琥珀」になります。 最も古くは1000年を越す琥珀もあるかもしれませんが、厳密な年代を特定することは困難を極めます。 多くのものが500年から200年程度と推測できますが、正確にはわかりませんのでご了承下さい。 チベットやヒマラヤ山岳民族での人気を尻目に日本ではトルコ石や珊瑚に比べて今一つ認知が足りません。 現地においては3種の神器中最も手に入れ難いと言っても過言ではないでしょう。 グラム辺りの単価も非常に高額となります。 只今市場に出回っているものの8割方はチベットで使われていたアンティークではなく、新しいものとなります。新しいものを古加工してそれらしくしているものもありますが、コーパルや加工品が流通しているのも事実です。 見分けるポイントとしては、ターコイズや珊瑚同様に古いもの特有の鈍い照りや摩耗痕になりますが、最も大切なのはやはり「信用」による取引です。  水晶と並ぶほど有名で人気のラピスラズリ。 遥か昔より人々を魅了し、装飾品として愛されてきたこの青い石ですが、最も古くは紀元前4世紀のシュメール文明であるウル遺跡ですでに交易品として採掘していたのがわかっています。 古代エジプトやメソポタミア、古代ローマでも装飾品として愛用され、人々を彩ってきました。 実はこのラピスラズリとう名前は通称にすぎず、「ラピスラズリ」という単体の鉱物組織は存在しません。 「方ソーダ石グループの鉱物を主成分とする岩石で、複数の鉱物の混合物(青金石・方ソーダ石・藍方石・黝方石・方解石・黄鉄鉱等)」をラピスラズリと呼びます。 つまりラピスラズリは鉱物の名前ではなく、複数の鉱物の混合体である岩石に付けられた宝石名なのです。 ラピスラズリの主成分である青金石は岩石ではなく鉱物です。 ややこしいですね。
水晶と並ぶほど有名で人気のラピスラズリ。 遥か昔より人々を魅了し、装飾品として愛されてきたこの青い石ですが、最も古くは紀元前4世紀のシュメール文明であるウル遺跡ですでに交易品として採掘していたのがわかっています。 古代エジプトやメソポタミア、古代ローマでも装飾品として愛用され、人々を彩ってきました。 実はこのラピスラズリとう名前は通称にすぎず、「ラピスラズリ」という単体の鉱物組織は存在しません。 「方ソーダ石グループの鉱物を主成分とする岩石で、複数の鉱物の混合物(青金石・方ソーダ石・藍方石・黝方石・方解石・黄鉄鉱等)」をラピスラズリと呼びます。 つまりラピスラズリは鉱物の名前ではなく、複数の鉱物の混合体である岩石に付けられた宝石名なのです。 ラピスラズリの主成分である青金石は岩石ではなく鉱物です。 ややこしいですね。 ラピスラズリはスカルン(結晶質石灰岩)中に産出し、世界に出回るほとんどのラピスはアフガニスタンで採掘されているものです。 驚くべきことにバダクシャン(Badakhshan)地区のラピス鉱床は6000年もの長きに渡りラピスラズリを産出しています。 ごく少量がアメリカ、シベリアやミャンマーでも確認されておりますが、最高質のラピスラズリは依然としてアフガニスタン産といえます。 古くから採掘が確認されているチリ・Ovalle地域のラピスが唯一、アフガンラピスと競合しうるクオリティを持つと言われていますが、産出量はアフガニスタンには及びません。 最高質のラピスは深みのある神秘的な藍色に少量の黄鉄鉱と方解石が星屑のような情景を創り出しているものです(しかし方解石が強すぎて白い亀裂が見られるのは好まれません)。 それはまるで宇宙に浮かぶ天の川のようでもあります。
ラピスラズリはスカルン(結晶質石灰岩)中に産出し、世界に出回るほとんどのラピスはアフガニスタンで採掘されているものです。 驚くべきことにバダクシャン(Badakhshan)地区のラピス鉱床は6000年もの長きに渡りラピスラズリを産出しています。 ごく少量がアメリカ、シベリアやミャンマーでも確認されておりますが、最高質のラピスラズリは依然としてアフガニスタン産といえます。 古くから採掘が確認されているチリ・Ovalle地域のラピスが唯一、アフガンラピスと競合しうるクオリティを持つと言われていますが、産出量はアフガニスタンには及びません。 最高質のラピスは深みのある神秘的な藍色に少量の黄鉄鉱と方解石が星屑のような情景を創り出しているものです(しかし方解石が強すぎて白い亀裂が見られるのは好まれません)。 それはまるで宇宙に浮かぶ天の川のようでもあります。 近年になって産出が減少しているという噂を聞きますが、情報の真相は定かではありません。 市場にはパウダーで作った練り物も多く、鮮やかすぎるブルーや不自然な金粉は練り物の場合が多いといえます。 ラピスラズリは硬度5.5ですので、決して強い石ではありません。 固い金属などと触れ合っているとスクラッチ傷ができますのでご注意ください。 また、酸性成分にも弱いので、汗や化粧品などはなるべく避け、ついてしまった時は柔らかい布で拭いてあげるようにしましょう。
近年になって産出が減少しているという噂を聞きますが、情報の真相は定かではありません。 市場にはパウダーで作った練り物も多く、鮮やかすぎるブルーや不自然な金粉は練り物の場合が多いといえます。 ラピスラズリは硬度5.5ですので、決して強い石ではありません。 固い金属などと触れ合っているとスクラッチ傷ができますのでご注意ください。 また、酸性成分にも弱いので、汗や化粧品などはなるべく避け、ついてしまった時は柔らかい布で拭いてあげるようにしましょう。 現地ネパールやヒマラヤ文化圏でもラピスラズリの装飾品は見られますが、ターコイズや珊瑚ほど需要が強いわけではありません。 アンティークなラピスほど価値がある、という話もあまり聞きません。 また、カトマンズにおいては良質アフガニスタン産ラピスラズリが減少傾向にあり、入手困難になっています。 これはアフガニスタン商人がラピスラズリを持ってこなくなったことによるものですが(2008年以来)、天然石の市場がバンコクや香港に移りつつある為です。 かわってジャイプールで削ったラピスラズリが多く流入してくるようになり、こちらは廉価なのですが若干色みが着色のように思えますので現在調査中です(当サイトでは取り扱っておりません) 余談ですが、ヨーロッパルネッサンスの絵画の美しい青色はラピスラズリを削って溶かした岩絵の具によるものなのです。 同様にネパール・チベットでもタンカと呼ばれる仏画に使用している青色はラピスラズリによるものです。
現地ネパールやヒマラヤ文化圏でもラピスラズリの装飾品は見られますが、ターコイズや珊瑚ほど需要が強いわけではありません。 アンティークなラピスほど価値がある、という話もあまり聞きません。 また、カトマンズにおいては良質アフガニスタン産ラピスラズリが減少傾向にあり、入手困難になっています。 これはアフガニスタン商人がラピスラズリを持ってこなくなったことによるものですが(2008年以来)、天然石の市場がバンコクや香港に移りつつある為です。 かわってジャイプールで削ったラピスラズリが多く流入してくるようになり、こちらは廉価なのですが若干色みが着色のように思えますので現在調査中です(当サイトでは取り扱っておりません) 余談ですが、ヨーロッパルネッサンスの絵画の美しい青色はラピスラズリを削って溶かした岩絵の具によるものなのです。 同様にネパール・チベットでもタンカと呼ばれる仏画に使用している青色はラピスラズリによるものです。